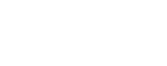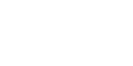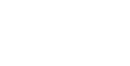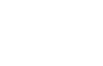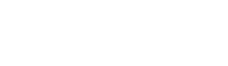歯周病の治療 Q&A
歯周病にかかった理由
Q.金属の歯(あるいはポーセレンの歯)を10年前に入れたのですが、
最近少し動く感じがしたので歯科医院に受診すると歯と入れた金属の歯が合わなくなったため
歯周病にかかったと言われました。
外側の金属は減ることはないと思いますが、どうして歯周病にかかってしまったのでしょうか?
A. 人工のかぶせ物や詰め物を入れた歯は、
どんなに適合が良くてもセットしてからの手入れが悪くなると歯との境目にプラークが溜まり、
歯周病が起こってきます。ポーセレンの治療の場合は保険外の治療でお金もかかっていますので、
治療を受けた歯は特に歯磨きに注意して、歯科医院でのメインテナンスが必要となります。
Q.入歯のばねがかかっている歯がぐらぐらしてきたので、
歯科医院に行ったら歯の周りの骨がなくなったと言われました。これも歯周病のせいでしょうか。
A. 入歯のばねがかかっている歯は他の歯よりも負担が大きいので、
長い間使用していると歯を支えている骨が吸収されることがあります。
これ自体は歯周病ではありません。 ところが、
入歯のばねがかかっている歯はプラークがつきやすいので、
歯周病に侵される危険も高くなりますので気をつけて下さい。
治療について
Q.何回も歯磨き指導を受けているのですが、
ある程度磨けている
(スコアが20%くらいだと言われました)のにもっと丁寧に磨くように、といわれています。
自分でもこれくらいが限界だと思いますし、
自分で磨くよりも治療をしていただいた方が早く治るのではないでしょうか?
A. 歯ブラシをしていて大事なのはその時にどれくらい磨けていたか、ということだけでなく、
自分で自分の歯を全て見落とすことなく磨くことができることです。
歯科医院には毎日通うわけでもありませんから、治療に通院している期間を通じて、
磨き残しができるだけないように、磨けないところがないようにしてください。
もしも、全部自分で出来なくても治療で通院している間は
歯科医院で歯周病の治療の一環としてプラークをしっかり除去してくださいますし、
治療後も定期的にリコールしていただければ、歯周病が再発する可能性も少ないです。
Q.歯周病の治療に歯石をとったら歯ぐきが下がってすき間が開いてきました。
それに食べ物がはさまったり、息が抜けてしゃべりにくくなったりしています。
どうしてでしょうか。またどうしたらいいのでしょうか。
A. 歯石を取った後歯肉が下がったのは、歯の間を塞いでいた歯石を除去したこと、
歯石を除去したことで歯肉の腫れがひいたためです。
すき間が開くと、結果的に食べ物がはさまりやすくなります。
また御指摘の通り、息が抜けて話しにくくなります。
食べ物がはさまるのはある程度は加齢による自然なものといえますが、挟まったままですと、
これが原因でプラークが蓄積して歯周病が再発してしまいますので、
きちんと歯ブラシや歯間ブラシで除去しなくてはなりません。
息が抜けるのはある程度仕方ないことといえますので、このような症状が気になり、無くしたいのであれば、
すき間の開いた歯にそれぞれ金属やポーセレン(白い歯)のかぶせ物により対処できます。
しかしこの場合歯を削る必要がありますので歯科医師によく相談してください。
Q.特に症状がなかったのですが、歯周病の治療ということで歯石をとった後で、
歯がしみたり、歯が少し浮いた感じがして噛みにくくなりました
。治療を受けたのに、なぜ症状が出てきてしまうのでしょうか。
また、治るのでしょうか、心配です。
A. 歯周病の場合、歯と歯肉の間にできたポケットの中に歯石は付着しています。
この歯石を取ると歯の根の部分が露出します。
この部分は歯の神経に近いので、冷たいものがしみやすくなります。
この場合、しっかりと磨いていればポケットが浅くなってしみなくなりますが、しみるのには個人差もあり、
症状が激しい場合は、歯の知覚が過敏になったことに対する治療が必要になります。
歯石を除去した後に歯が浮いた感じがするのは、
歯石を除去する時に働く力が歯を噛む方向と逆になっている場合が多いからです。
歯肉のポケットの中から外に向かって掻き取りますので、歯石を除去した後で浮いた感じがするのです。
歯はかなり弱っていて抜いた方が良い場合もあります。
検査について
Q.歯ぐきの検査をするときや歯石を取るときにチクチクと痛いのですが、どうしてでしょうか。
A. 歯肉の検査では、歯と歯肉の隙間である歯周ポケットの深さを測ります。
また歯石を取るときは歯肉の上に覆い被さるように付いている歯石を取り除くので
どうしても器具の先端が炎症を起こして敏感になっている歯肉に触れます。
しかしそれが我慢できないようであれば、表面麻酔(スプレー式の麻酔)を用いるなどの方法もありますので歯科医師に相談して下さい。
Q.歯石はどれくらいおきに歯科医院にとりに行ったらいいのでしょうか
A. 本来、適切な歯磨きができていれば歯石は付きません。
また歯石の付きやすさにも個人差があります。歯磨きの指導を受けても時間がたてば、
その記憶が曖昧に疎かになりやすいのも事実です。 通常は1年に3回~4回が良いと言われています。
また、かかりつけの歯科医師(歯科医院)を決めて、歯石のつきやすさを継続してみていただければ、
どのくらいの期間で定期健診を受ければよいかわかります。
Q.歯石を取るときにレーザを使うと痛くないと聞いたのですが、本当でしょうか?
A. 歯科用レーザには様々な種類があります。
またレーザ以外にも歯石を取る器具はいくつもあります。
いずれの器具を用いても痛くなく歯石を取ることは可能でしょう。
歯石の中には歯の周囲のポケット深くまで入り込んでいるものがあります。
普通その場合は麻酔して取る必要がありますが、レーザを用いると麻酔が少量あるいは必要ない場合があります。
Q.検査の時にエックス線写真を10枚以上撮影したのですがそんなに枚数が必要なのでしょうか?
A. エックス線写真検査は口内法と呼ばれる方法とパノラマエックス線写真と呼ばれる方法とがあります。
前者は、1本1本の歯や歯周組織(骨)の状態を詳細に知ることができる方法で、
上下左右と前歯と奥歯をそれぞれ撮影しますので、10~14枚撮影します。
後者は顎関節を含めた上下の顎の骨の状態まで把握できます。
被爆量についてはどちらの方法も問題はありません。
Q.歯ぐきが腫れたときに歯科医院へ行くと、ポケットといわれる部分を洗って薬をくれます。
それで腫れは治るのですが、数ヶ月たつとまた腫れてしまいます。どうしてでしょうか?
A. 歯周ポケットは深くなると歯ブラシが届きにくく、ポケットの中の細菌を自分で清掃することは困難です。
そこで歯科医院ではポケットの中を洗うことと抗生物質などの飲み薬で症状は軽減させます。
ところが、ポケットの中にはまだ細菌を含んでいる歯石が歯の根の部分に付着したまま残っています。
これを放置すると歯周ポケットの中に細菌が繁殖することになり、
炎症が進行するので、歯肉(歯ぐき)が再び腫れてくるのです。
抜歯について
Q.重度の歯周病にかかっていると診断されました。
早期に抜いた方が良いといわれたのですが、なんとか歯を残せないのでしょうか。
A.保存が無理になっている歯をいつまでも残しておくと、隣の歯を支えている骨が無くなってきてしまいます。
またいたずらに抜いたほうが良い歯を残していると、最終的に抜いた後で入歯も難しくしてしまったり、
腫れたり痛みがでるなどの不快症状を繰り返す原因になります。
Q.自分の歯を残してもらいたいので歯科医院に行ったのですが、
抜いた方が良いと言われました。歯周病の治療をしても自分の歯が残らないのでしょうか。
A. 歯周病の治療により、歯肉(歯ぐき)の炎症はほとんどなくなり、歯周病の進行はほぼ止まります。
ところが、来院していただいた時点で、歯を支える中心となる骨がなくなっていると、
歯肉があっても歯が抜け落ちてしまいますし、しっかりと噛むことができません。
ですから症状が進んでしまった歯は抜くと診断されたのです。
手術について
Q.歯周病の歯肉を外科手術すると言われたのですが、怖いです。実際にはどのような治療で、時間はどれくらいかかるのでしょうか。またその後、どうなるのでしょうか。
A. 歯周病に対する外科手術には、腫れが引かない歯肉を除去するもの、
歯の周囲にあるポケットを除去するもの、歯を支えている骨を移植するもの、
歯を磨きやすいように歯肉や粘膜の形を変えるものなどがあります。
外科手術に必要な時間は治療対象となる歯の本数にもよりますが約1~2時間かかります。
治療の後は、縫合して、包帯しますので、1週間後に縫合と包帯を除去し、経過を1~数ヶ月経過を追います。
怖がる必要はありませんので、手術の内容を担当医に聞いて、よく相談して下さい。
Q.歯周病の再生治療はどの程度、歯ぐきや(歯槽)骨が再生するのでしょうか。
A. 歯周病の発症時期にかかわらず、治療により再生は起こります。
しかし、再生治療の適応となるケースが限られています。
一般的には中等度の歯周病が対象となります。
また、患者さんの年齢や体力、免疫力、御自身による歯磨きなどの努力により大きく左右されます。
歯周病の再生治療はどのくらいの期間で再生するのでしょうか 再生は治療の直後より始まりますが、
見かけ上の治癒が起こってからも継続し、通常半年以上かかります。
また、再生した状態を維持させるには定期的なメインテナンスを継続されることが必要となります。
Q.現在行われている歯周病の再生治療はどれくらい費用がかかりますか?
A. 近年、再生療法は様々な方法が開発されてきていますが、
まだ我が国では一部の大学病院を除いて保険診療の中で使用することは認められていません。
また再生療法に主に用いられる膜やジェルは材料費だけでも1回分で2万円近くします。
詳細については近くの大学病院や専門医のいる歯科医院に相談して下さい。